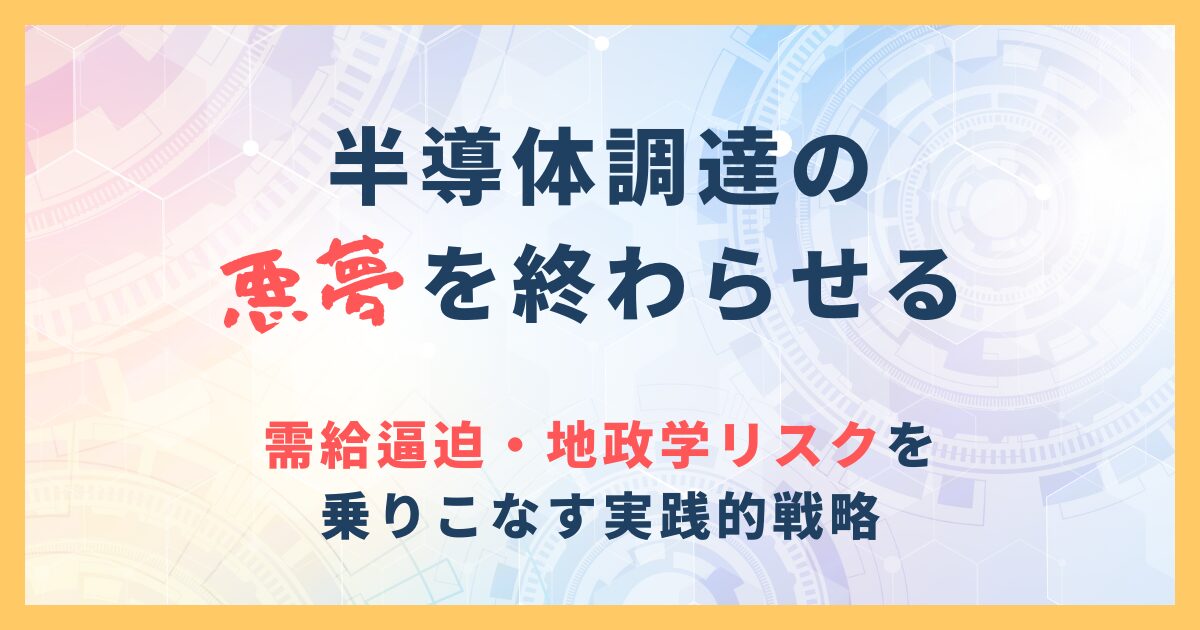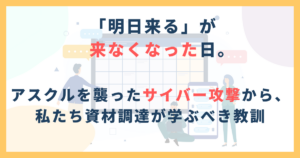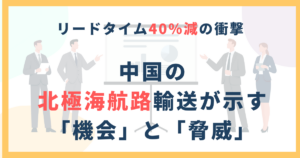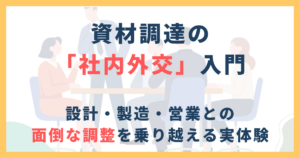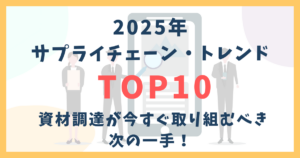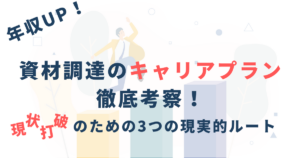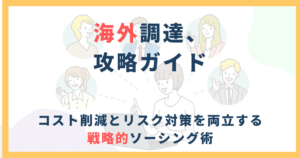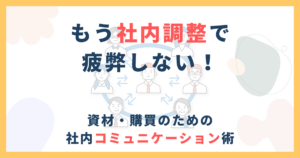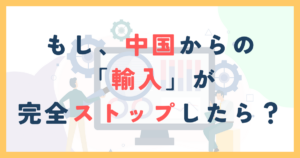また半導体の納期が延びたのか…もうどうすればいいんだ?
この言葉、最近よく聞きませんか?
そんなあなたに、20年のキャリアから生まれた実践的なノウハウをお届けします。
絶望的な現実!半導体供給網を揺るがす地殻変動

私たちが直面している今回の半導体不足は、一過性の現象ではありません。
需要と供給のバランスが崩れたという単純な話ではなく、業界の根幹を揺るがすほどの巨大な地殻変動が起きているのです。
前提:驚くほど複雑で脆弱な国際分業のリアル
半導体という製品がいかに危ういバランスの上で成り立っているか、ご存じでしょうか?
これは特定の一国では決して作れない、グローバルな製品なのです。
| 工程 | 主な国・地域 | プレーヤー(例) |
|---|---|---|
| 設計 | 米国 | NVIDIA, Qualcomm |
| 製造装置 | 日本・蘭・米 | 東京エレクトロン, ASML |
| 前工程(最先端) | 台湾 | TSMC |
| 後工程(組立・検査) | 中国・東南アジア | ASE, Amkor |
この中のどこか一つでも止まってしまえば、サプライチェーン全体がドミノ倒しのように機能不全に陥る。私たちはそんな細い糸の上を歩いているのが現実です。
AI向け半導体が他の用途の生産能力を奪い取る
古いアナログ半導体には関係ないでしょ?
もしそう思っていたら、それは危険なサインかもしれません。
今の半導体市場では、生成AIやデータセンターに使われる高性能な半導体が、極めて高い収益を生み出しています。
半導体工場は限られた生産ラインを、その「AI向け半導体」の製造に優先的に割り当てる傾向にあります。
その結果、利益率の低い私たちが必要とする汎用的な半導体の生産は後回しにされ、いつまで経ってもモノが作られない、という事態に陥りやすくなっているのです。
地政学というチェス盤:分断されるサプライチェーン
さらに事態を複雑にしているのが、地政学リスクです。
特に米中対立は、私たちの部品表(BOM)を直撃しました。
米国による中国への先端半導体輸出規制強化により、企業は「中国市場向けの製品」と「それ以外の市場向けの製品」で、サプライヤーや部品そのものを分けざるを得ない状況に追い込まれ始めています。
最大の懸念:台湾有事のリスク
世界の先端半導体製造を一手に担う台湾で万が一のことがあれば、スマートフォンから自動車まで、あらゆる製品の生産が世界的にストップするでしょう。
これはもはや遠い国の話ではなく、私たちの事業継続計画(BCP)において最も考慮すべきシナリオの一つなのです。
悪夢のような脅威!最前線の調達担当者を襲う3つのリアル

マクロな環境変化を理解した上で、今度は私たちの足元で起きている、より生々しい脅威にがあります。
これらは、私が20年以上のキャリアの中で、今ほど深刻に直面したことのない、現場のリアルです。
① 供給制約:「2年待ち」とNCNR契約のプレッシャー
納期は、現時点で104週(=2年)です
コロナ禍前頃から、こんな回答が当たり前のように返ってくるようになりました。
2年後の生産計画なんて、どうなっているか予測できるでしょうか?
さらに厄介なのが、NCNR(Non-Cancelable/Non-Returnable)契約、つまり「キャンセル不可・返品不可」という条件です。
一度サインすれば、たとえ需要がなくなっても全量引き取らなければならない。このプレッシャーの中で、私たちは日々、発注判断を迫られているのです。
なぜNCNRなのか?業界の裏事情
しかし、実は、サプライヤもこの条件にしなければいけない理由があるんです。
みなさん供給難の時にはいくつもの代理店に在庫を確認しますよね。いつ入ってくるか分からない注文。保険のために手当たり次第に注文を入れる発注者がたくさんいます。
そして、どこかで入手できれば、他の注文をキャンセル。まるで、ホテルや居酒屋・ゲーム機を気軽に予約して、直前にキャンセルする現象と同じです。
でもメーカからしたら大問題。その膨れ上がった注文をうのみに大増産しても、不良在庫をかかえることになりますからね。
② 偽造品リスク:「香港にあった」その一報が悪夢の始まりだった【実体験】
最も恐ろしいのが偽造品のリスクです。
世界中から在庫が枯渇し、いよいよ生産ラインの停止が目前に迫っていた時でした。
社内は「何でもいいから探せ!」という雰囲気で、連日、世界中の代理店やブローカーに連絡を取り続けていました。
そんな時、一筋の光が差し込みます。小さな取引ながらも断続的に取引実績がある香港の業者から、「少量だが在庫が見つかった」との一報。
まさに天の助け!私はすぐに業者の登記情報を再確認し、送られてきた製品の写真で未開封であることも確かめ、購入を決断しました。
しかし、悪夢はそこからでした。数日後、私は担当者から会議室に呼ばれ、衝撃的なレポートを見せられました。
外観上のシリアル番号の印字フォントに、正規メーカー品との微細な差異を確認。
また、X線透過検査において、内部のリードフレームが正規品と一致しない。
電気的特性試験においても、規格値を逸脱する項目が複数見られたため、本製品は正規生産品ではないと判定する
うぎゃ~。
血の気が引きました。あの時、もし真贋判定をせずにラインに投入していたら…
市場で大規模な製品不具合を引き起こし、賠償の嵐で会社の信用を失墜させていたかもしれない。
この経験から得た教訓・・・
・非正規代理店からの購入は、業者の与信や現品の外観確認だけでは全く不十分
・やむを得ず購入する場合は、真贋判定サービスの活用が最後の命綱になる
反撃の狼煙!サプライチェーン強靭化へ踏み出す5つのアクション

絶望的な話が続きましたが、ここからが本題です。
困難な状況だからこそ、私たち調達部門が企業のヒーローになれるチャンスです。
受動的な購買担当から、能動的にサプライチェーン強靭化の担い手へと生まれ変わるための、5つの具体的なアクションを提案します。
①「発注先」から「戦略的パートナー」へ
旧来の「買い手と売り手」という関係性を、今すぐ捨て去るべきです。
これからは、主要なサプライヤーと未来を共に創る「戦略的パートナー」としての関係を築く必要があります。
②「勘と経験」から「データドリブン」へ
「見えないものは管理できない」。
これはサプライチェーンマネジメントの鉄則です。
いつ、どこで、誰が、何を作っているのか、どれだけ在庫を持っているのか。
この情報をリアルタイムで可視化するために、SCM(サプライチェーン・マネジメント)ツールへの投資は不可欠です。
実践的なスタート方法
いきなり何千万円もするシステムを導入する必要はありません。
まずはExcelベースでもいいので、サプライヤーの先のサプライヤー(Tier2, Tier3)の生産に関する情報を収集し、リスクマップを作成することから始めてみてください。
③「悪」から「戦略的武器」へ:在庫の再定義
長年、在庫は「コストを圧迫する悪」と見なされてきました。
しかし、予測不可能な混乱が常態化した今、在庫は「事業継続を保証するための戦略的な保険」として再定義されなければなりません。
重要なのは、やみくもに在庫を積むのではなく、BCP(事業継続計画)の観点から、どの部品を、どれだけ、どこに保管すべきかを戦略的に決定することです。
④「後工程」から「最前線」へ:設計段階から関与する
サプライチェーン強靭化の最も強力な手段は、実は発注書が発行されるずっと前、設計段階にあります。
私たち調達担当者は、仕様が確定するのを待つのではなくもっと積極的に、部品開発、できれば製品企画の初期段階から関与していくべきです。
- 単一のメーカーしか作っていないような特殊な部品(シングルソース品)の採用を避けるよう、技術部門に働きかける
- あらかじめ代替可能な部品を複数認定しておく「マルチソース化」を推進する。
これを「サプライチェーンのための設計(Design for Supply Chain)」と呼びます。
技術部門との壁は厚いかもしれませんが、粘り強く対話し続ける価値は十分にあります。
⑤【未来予測】チップレット技術がもたらす調達革命
最後に、少し未来の話を。
今、「チップレット」という技術が注目されています。
これは、一つの大きな半導体を作るのではなく、機能ごとに作られた小さな半導体(チップレット)をブロックのように組み合わせて、一つのパッケージに収める技術です。
「このCPUに、A社の通信機能とB社の画像処理機能を組み合わせた半導体が欲しい」といった、より柔軟な選択が可能になる点が革命的です。
特定の半導体メーカーの製品に縛られることなく、最適な機能の組み合わせを調達できる。
これは、サプライヤーへの依存度を下げ、サプライチェーンに新たな柔軟性をもたらすゲームチェンジャーになる可能性を秘めています。
まとめ:サプライチェーン強靭化の鍵を握るのは、戦略的な調達部門だ

この記事では、半導体供給網の構造的な変化から、失敗談、そして未来に向けた具体的なアクションプランまでをお話ししました。
この厳しい環境は、間違いなく私たちにとって大きな試練です。
しかし、見方を変えれば、これは調達という仕事の価値を再定義し、自らの専門家としての市場価値を証明する絶好の機会ではないでしょうか。
もはや私たちは、単なる値下げ交渉請負人のコストカッターではありません。
企業の未来を左右するサプライチェーン強靭化の鍵を握る、戦略的エンジンなのです。
今すぐできる3ステップ
①リスクの棚卸しをする
まずは担当している主要な半導体について、サプライヤーの国、製造拠点、代替品の有無などを一覧表に書き出してみましょう。
②仲間を作る
書き出したリスクマップを持って、技術部門や品質保証部門のキーマンと「相談」してみてください。
一人で抱え込まず、仲間を作ることが重要です。
③学び続ける
この記事をブックマークし、チーム内で共有してください。
そして、今後の記事もチェックしていただけると嬉しいです。
一緒にこの困難な時代を戦い抜きましょう!