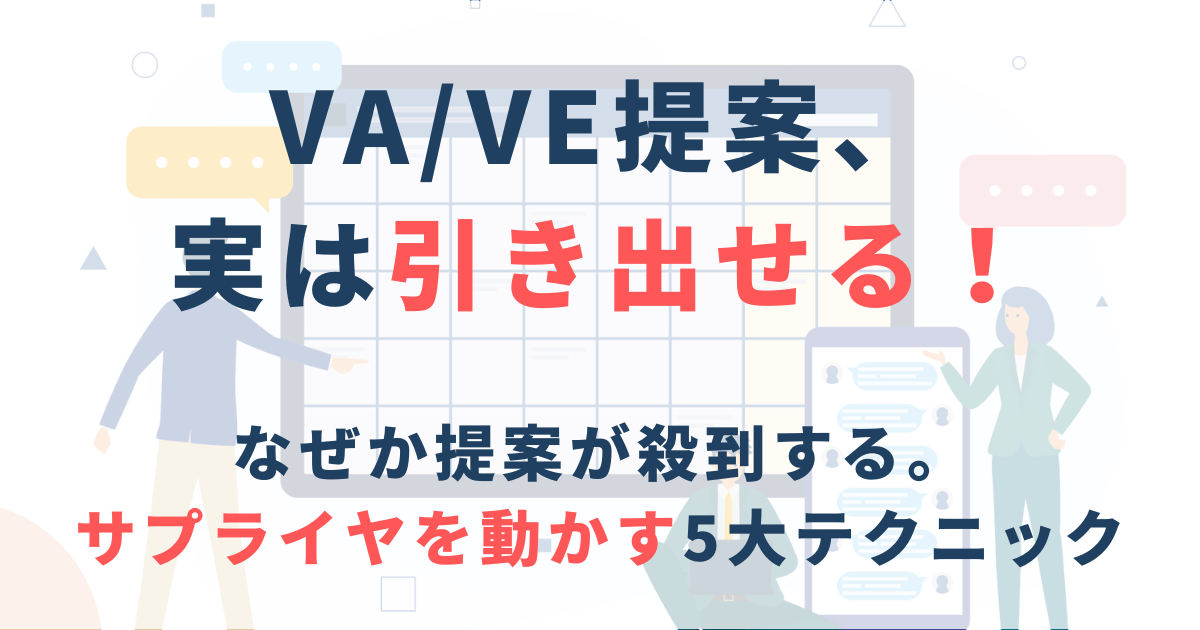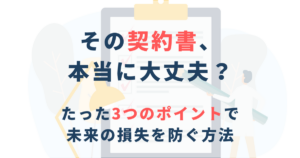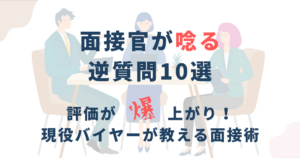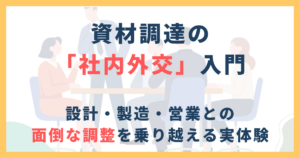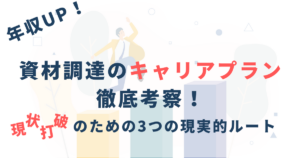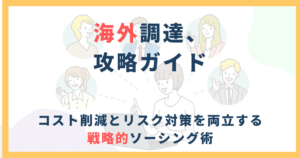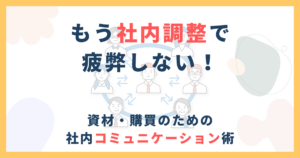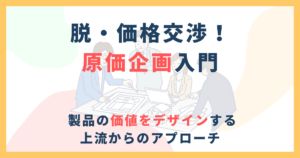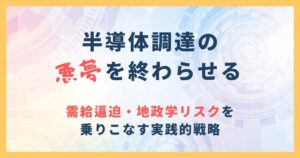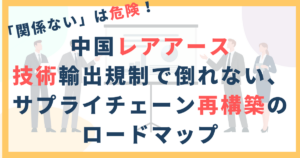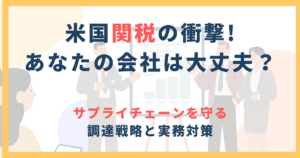「またコストダウンの話か…」
サプライヤーさんの心の声が聞こえてきそうですね…
もしあなたが今、そう感じているなら、この記事はきっと役に立ちます。
実を言うと、これは10年以上前の私が、メーカーさんの会議室で、凍りつくような沈黙の中で感じていた焦りそのものなんです。
この記事は、単なるコスト削減のテクニック集ではありません。
サプライヤーを「コスト削減の相手」から「価値創造のパートナー」へと変え、あなたの市場価値を劇的に高めるための、私の20年間の試行錯誤の記録です。
この記事で得られること
・サプライヤーが思わず協力したくなる「VA/VE提案の依頼方法」
・コスト削減と価値向上を両立させる「珠玉の5大テクニック」
・「待ち」の調達から脱却し、市場価値を高める「戦略的な思考法」
【愕然】あなたのVA/VE、”コストカット”で止まっていませんか?

まず、大前提の確認から。
VA/VEと聞くと、多くの人が「コスト削減」を思い浮かべます。
もちろん、それは間違いではありません。しかし、本質はそこじゃない。
VA/VEの生みの親であるL.D.マイルズが提唱した数式を、もう一度思い出してみましょう。
Value (価値) = Function (機能) / Cost (コスト)
この式が示す通り、価値を高める方法は4つあります。
- 機能はそのままで、コストを下げる
- コストはそのままで、機能を上げる
- 機能を上げ、コストを下げる
- コストを上げるが、それ以上に機能を上げる
多くの現場で、VA/VEは1の「コストを下げる」活動に終始してしまっています。
ですが、真にパワフルなのは、
・サプライヤーを巻き込んで2の「機能を上げる」こと、
・機能とコストの両方にアプローチすること
なのです。
「そんなことは分かっているよ」という声が聞こえてきそうですね。
ええ、私も頭では理解していました。あの大阪での苦い経験をするまでは。
VA/VEは、単なるコスト削減活動にあらず。
それは、「製品の価値を最大化するための、サプライヤーとの共同事業である」と捉え直すことから、すべてが始まるのです。
【絶望】なぜ提案は出てこない?サプライヤーが口を閉ざす冷たい理由

「VA/VE提案をお願いします!」と依頼しても、「はいはい、わかりました」 とはいうものの、その後は梨のつぶて。
なぜ彼らは協力してくれないのか?と悩んでいた時期が私にもありました。
コスト削減目標達成へのプレッシャーから、私はとあるサプライヤーに意気揚々と「VA/VEの提案をお願いします」と協力依頼をしたのです。
しかし、返ってきたのは重い沈黙と、ベテラン技術部長からの
「…我々に、具体的に何を求めていますか?」
という、あまりにも冷静な質問でした。
頭をガツンと殴られたような衝撃でした。
「なにをって、コストを下げるための提案です。」
「う~ん」
といったきり、そのベテラン技術部長は押し黙ってしまいました。
その時は私は、彼らが提案できない理由を、彼らのやる気のせいにしていました。
しかし後でよく考えると原因は100%、私にあったことに気づきました。
サプライヤーが口を閉ざす3つの理由
サプライヤーが口を閉ざす理由は、突き詰めると3つです。
- 情報不足(何をすればいいか分からない)
あなたは「どんな機能を実現したいのか」「どんな顧客課題を解決したいのか」という目的を伝えていますか?「とにかくコストを下げろ」では、彼らは動けません。
彼らはエスパーではないのです。
2. メリット不在(やっても得しない)
VA/VE提案に多大な工数をかけた結果、得られるのが「ありがとう」の一言と、さらなるコスト削減要求だとしたら?
あなたなら、やりますか?正直、私ならやりません。
3. 関係性の欠如(そもそも、あなたを信用していない)
これが最も根深く、そして最も重要な問題です。
日頃から無理な要求ばかり突きつけ、パートナーとして尊重してこなかった相手のために、誰が知恵を絞るでしょうか。悲しいけれど、これが現実。
【希望】提案の”土壌”を耕す!戦略的パートナーシップという光明

一人でへこんでいた私を救ってくれたのは、意外にも、あの時最も冷たい視線を向けてきたサプライヤーの技術部長でした。
後日、私は彼の会社に単身訪問して、頭を下げました。
「何も分かっていませんでした。
再度協議させてください」
彼は多くを語りませんでしたが、帰り際にポツリと言ったのです。
「我々は、あんたの会社の製品がどうなってほしいのか、知らないんだよ」
この一言が、私の調達キャリアの転換点となりました。
VA/VE提案は、依頼して出てくるものではない。
良質な提案が自然と生まれてくる「土壌」を、時間をかけて耕す必要があるのです。
「そんな悠長なこと言ってられない!」
よく分かります。
目の前のコスト目標が厳しいのに、関係構築なんて遠回りだと感じるかもしれません。
しかし、急がば回れ。目先の値引き交渉で削れるコストなど、たかが知れています。
一方で、戦略的なパートナーシップから生まれる価値は、時に年間調達額の10%を超えるインパクトを持つことすらあるのです。
良質な提案が自然と生まれる土壌を耕す3つのアプローチ

では、具体的にどうやって土壌を耕すのか?
私が実践してきた3つのアプローチを紹介します。
| アプローチ | 具体的なアクション | 目的・効果 |
|---|---|---|
| 定期的な情報共有会 | 月に1度、主要サプライヤーと「雑談」する場を設ける。テーマは「最近の技術トレンド」や「業界の課題」など、直接の取引以外の話も歓迎する。 | 相互理解の深化、信頼関係の醸成 |
| 戦略ロードマップの開示 | 自社の3〜5年先の製品開発ロードマップや、解決したい技術的課題を、NDA(秘密保持契約)締結の上で共有 | サプライヤーに「自分たちが貢献できる場所」を意識させ、当事者意識を育む |
| 「期待」の言語化 | 「御社の〇〇という技術があれば、弊社のこの課題を解決できるかもしれません」と、具体的に期待していることを伝える。 | 「コスト削減パートナー」から「技術パートナー」へと、相手の自己認識を変える。 |
【興奮】サプライヤーを動かす!明日から使える珠玉の5大テクニック

さて、土壌が少しずつ肥沃になってきたら、いよいよ種まきです。
ここでは、私が数々の失敗の末にたどり着いた、サプライヤーの心を動かし、具体的な提案を引き出すための珠玉のテクニックを5つ、包み隠さずお伝えします。
テクニック1:魅力的な「提案依頼書(RFP)」の書き方
「VA/VE提案募集」という件名のメールを送るだけでは、三流です。
本当に優れた提案が欲しいなら、RFP(提案依頼書)の中身をとことん工夫しましょう。
ポイントは「課題」と「制約」を明確に、しかし「解決策」は限定しないこと。
「部品Aのコストを10%削減する提案を求む」
「部品Aが使われる製品Xは、3年後に市場投入されるモデルYの後継機です。
顧客からは『さらなる軽量化』が求められており、目標重量は-15gです。
コストは現行同等以下が望ましいですが、画期的な軽量化が実現できるなら、コストアップも検討します。
皆さんの技術で、この課題を解決するアイデアをいただけませんか?」
目的と背景を語り、相手をワクワクさせることができれば、あなたの想像を超える提案が舞い込んでくるはずです。
テクニック2:成果配分型インセンティブの設計
きれいごとだけでは、ビジネスは動きません。
サプライヤーが本気で知恵を絞る「うまみ」を設計することも、調達担当者の重要な仕事です。
以前、単純に
「削減額の50%の値上げを認める=つまり、100円下げられる提案を50円下げるだけにとどめる」
(数字は仮)という約束をしたことがあります。
結果どうなったか?
サプライヤーは目先のコスト削減ばかりを追い求め、長期的な品質や信頼性を度外視した提案ばかりを持ってくるようになりました。
この失敗から学んだのは、インセンティブは「生み出したトータルバリュー」に対して支払うべきだということ。
例えば、コスト削減額だけでなく、軽量化や性能向上といった「機能向上」も金額換算し、その総額に対して成果を配分するのです。
テクニック3:特別感を演出する「限定情報」の提供
人は誰しも「あなたは特別だ」と言われたい生き物。
これは法人であっても同じです。
すべてのサプライヤーに同じ情報をばらまくのではなく、本当に信頼しているパートナーにだけ、そっと限定情報を提供してみましょう。
「この話、まだ社内でも一部の人間しか知らないんですが…
来期、我々は〇〇という新市場への参入を計画しています。
そこで、御社の△△という技術が活かせないかと考えていまして…」
この「あなただけ」という特別感が、相手の心を強く揺さぶり、強固なパートナーシップへと繋がっていきます。
テクニック4:サプライヤー表彰制度の導入
個別の関係構築と並行して、会社として「価値ある提案を歓迎する」という文化を醸成することも重要です。
その最も有効な手段が、サプライヤー表彰制度の導入。
多くの大手企業では、サプライヤーを表彰しているのは有名な話です。
彼らはコスト貢献だけでなく、「技術開発賞」や「品質管理優秀賞」といった多様な物差しでサプライヤーを評価しています。
これにより、その大手企業に認められたという栄誉が、サプライヤーにとって最高のモチベーションとなり、さらなる改善努力へと繋がる好循環が生まれているのです。
テクニック5:経営層同士のトップ会談の設定
最後のテクニックは、いわば奥の手。
現場担当者レベルでのやり取りに行き詰まりを感じたら、思い切って経営層同士の対話の場を設定しましょう。
「いきなりそんなの無理だよ!」と感じるかもしれません。
ええ、その通りです。しかし、これもやり方次第。
「弊社の社長(や開発部長)が、御社の〇〇技術に大変関心を持っておりまして、一度お話を伺えないかと申しております」
とボールを投げるのです。
相手の経営者も、自社の技術に誇りを持っているはず。
無下に断ることはないでしょう。
経営トップ同士が「未来を共創するパートナー」として握手できれば、現場の壁などいとも簡単に突破できることがあります。
まとめ:VA/VEは”引き出す”もの。明日から始めるための第一歩

長い道のりでしたが、いかがでしたでしょうか。
VA/VE提案は、待つものでも、要求するものでもありません。
それは、信頼という土壌を耕し、戦略という種をまき、対話という水を与えることで、ようやく芽吹くものなのです。
難しく考える必要はありません。さあ、今すぐできることから始めましょう。
今すぐ始める3つのステップ
- まず、あなたが担当する主要サプライヤーの中から、たった1社だけを選んでください。
そして、その会社のキーマン(技術部長や営業担当者)の顔を思い浮かべます。 - 次に、そのサプライヤーが得意な技術と、自社の製品で「もっとこうなったら顧客が喜ぶのに」という視点でその部品をどう変えればいいか、技術者と相談し、1つだけノートに書き出してください。
- 最後に、「〇〇の件で、一度ご相談させていただけませんか?御社の知見をお借りしたく…」と、
たった一通のメールを送ってみましょう。
VA/VEは、もはやコスト削減のツールではありません。
それは、あなたとサプライヤーが未来を共創するための「対話」そのものです。
あなたのその一通のメールが、会社を、そしてあなた自身のキャリアを大きく変える第一歩になる。
私は、そう確信しています。
価値創造の旅は、いつだって最高にエキサイティングですよ!