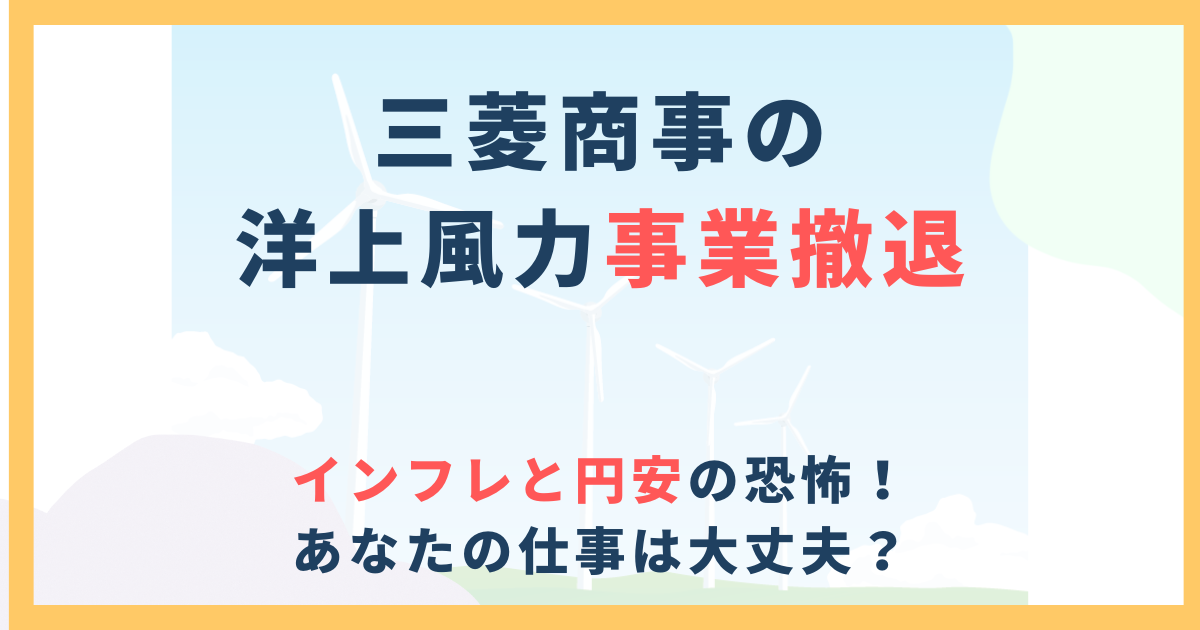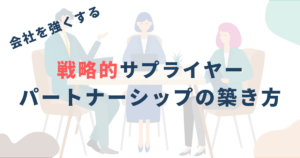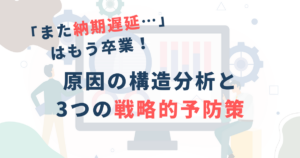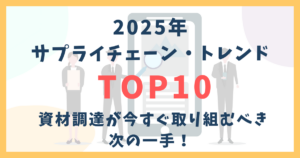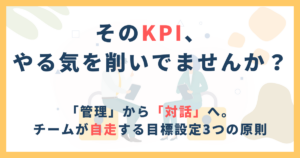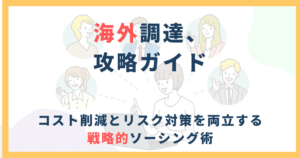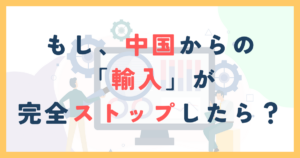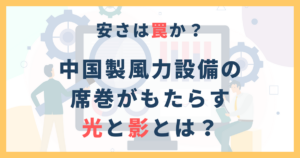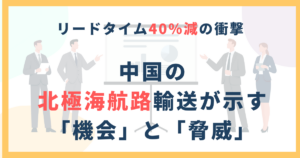先日、三菱商事が総事業費2兆円(※資材高騰後)規模の一大国家プロジェクト、洋上風力発電事業からの撤退を表明し、大きな衝撃が走りました。
 あかり
あかり三菱商事の洋上風力撤退?巨大プロジェクトの話で、うちみたいな中小企業には関係ないでしょ…?



それは大きな勘違いだ。
実はこのニュースの裏には、インフレ、円安、サプライチェーンの脆弱性といった、私たちの日々の調達業務に直結する深刻なリスクが凝縮されているんだよ。
もしあなたがそう感じているなら、その認識は少し危険かもしれません。
担当していたメーカーが突然事業を中止し、代替品の入手に追われた経験があります。
今回のニュースの本質は、あの日の悪夢と全く同じ構造をしています。
この記事を読めば、巨大プロジェクトの失敗事例から、あなたの会社が今すぐ取り組むべき具体的なアクションが明確になります。


【第1章】衝撃の事実!2兆円事業撤退が暴いた資材調達の“不都合な真実”
なぜ、総事業費1兆円と見込まれた巨大国家プロジェクトが、わずか数年で2兆円規模にまで膨れ上がり、ついには白紙撤回という結末を迎えたのでしょうか。
その本質は、「固定された売上(売電価格)に対し、調達コストが青天井になった」という、我々製造業の調達担当者にとって最も恐ろしい悪夢のシナリオそのものです。
この一件は、私たちに3つの重要な教訓を突きつけています。
資材調達における3つの教訓
- 「固定価格」という幻想
部品の長期契約担当者。市況が安定していたのをいいことに、「3年間の固定価格契約」という条件をサプライヤーに飲ませ、3年の発注継続と引き換えに大きなコスト削減を成果として社内で評価されたのです。担当者は大きな高揚感をえていました。
しかし、2年目に大地震が発生。サプライヤーの工場は直接の被害を免れたものの、原材料メーカーが被災し、樹脂原料価格は一気に30%も高騰。
サプライヤーからは悲鳴のような値上げ要請が来ましたが、担当者は契約書を盾に突っぱねました。
結果、どうなったか?
サプライヤーは契約を守るために赤字で供給を続けてくれましたが、その半年後、担当者の寝耳に水のうちに倒産してしまったのです。
「契約があるから大丈夫」は、幻想です。
相手が立ち行かなくなれば、契約書などただの紙切れ。
この三菱商事の事例も、まさに同じ構造を抱えていた可能性があるのです。 - 為替・インフレの恐るべき衝撃力
今回の洋上風力事業で、コストを押し上げた最大の要因は、急激な円安と世界的なインフレでした。
事業計画を立てた2021年頃は1ドル110円前後でしたが、2024年には一時160円を突破。
風車の主要部品は海外からの輸入品です。
仮に1億ドルの部品を調達する場合を考えてみましょう。
2021年の為替レート: 1=110円
2024年の為替レート: 1=160円
計算式:
計画時コスト: 1億ドル×110円/ドル=110億円
実行時コスト: 1億ドル×160円/ドル=160億円
結果:
為替変動によるコスト増: 160億円−110億円=50億円
これだけで50億円ものコストが増えるのです。
これは、海外から部品や原材料を調達する全ての日本企業が、今まさに直面しているリスクに他なりません。 - サプライチェーンの知られざる脆弱性
そもそも、なぜ風車を海外から買わなければならなかったのか?
ここに第二の教訓があります。
それは、「日本国内に大規模な風車のサプライチェーンが存在しない」という事実です。
特定国、特定企業への依存は、価格交渉力の低下を招くだけでなく、地政学リスクやカントリーリスク(相手国の政治・経済情勢の変化)が直撃する致命的なアキレス腱となります。
あなたの会社は大丈夫でしょうか?
「この部品は、中国のA社からしか買えない」「この材料は、台湾のB社に頼り切りだ」…
そんな状況はありませんか?
「大手だけの話」ではない



うちは自動車や電子部品じゃないし、そんなグローバルな話は関係ないんじゃないですか?
そう思った方もいるかもしれません。
しかし、本当にそうでしょうか?
例えば、あなたの会社が使っている機械の保守部品、その製造元は本当に国内ですか?
オフィスで使うPCやサーバーは?
もっと言えば、従業員の作業着の生地だって、その源流をたどれば海外の市況と無関係ではいられないはずです。
サプライチェーンは、蜘蛛の巣のように複雑に絡み合っています。
一見無関係に見える遠くの国の出来事が、気づいた時には自社の生産を脅かす事態に発展する。
それが現代の調達なのです。
【第2章】希望の光!担当者が明日からできる超実践アクションプラン



具体的に何をすれば良いのでしょうか?
毎日の業務で手一杯で、なかなかリスク管理まで手が回らなくて…
大丈夫。特別な時間を作る必要はありません。
まずは今やっている業務に「リスクの視点」を少しだけプラスすることから始めましょう。
1:サプライヤーとの「関係」を再点検する
コストや納期の話だけでなく、一歩踏み込んだ対話を始めてみませんか?
| チェック項目 | 具体的なアクション |
|---|---|
| リスクのヒアリング | 定例会で「最近、原材料や人件費で困っていることはないですか?」と聞いてみる。 |
| 現場の肌感覚 | 半年に一度はサプライヤーの工場を訪問し、現場の活気や設備の状況を自分の目で見る。 |
| 相互依存度の把握 | サプライヤーの売上における 自社の割合を把握する。 「うちはお客さんだ」という態度は捨てる。 |
2:契約書の「中身」を再点検する
「長期契約を結んでいるから安心」は禁物です。
今すぐ、主要サプライヤーとの契約書を確認してみてください。
価格スライド条項は入っているか?
原材料やエネルギー価格の変動を、取引価格に反映させるための条項です。
これがないと、市況が高騰した際に一方的にサプライヤーへ負担を強いることになり、供給不安に直結します。
為替リスクの取り決めは明確か?
海外取引の場合、どちらが為替変動リスクを負うのか、事前に経理部門と連携して対策(為替予約など)を検討していますか?
3:社内の「連携」を再点検する
調達は孤独な戦いではありません。
設計部門や品質保証部門を巻き込みましょう。
代替品の評価を進める
「この部品はこのサプライヤーからしか買えない」という状況(シングルソース)は最大のリスクです。
平時から代替サプライヤーや代替材料の評価を設計部門に依頼しておく。
設計変更を提案する
「この過剰なスペック、本当に必要ですか?この公差を少し緩めれば、他のサプライヤーでも作れるようになります」
といったV.A. (Value Analysis) 提案は、調達担当者だからこそできる価値ある仕事です。
【第3章】確信を得る!会社を守るマネージャが今すぐ打つべき戦略的布石
担当者レベルの活動と同時に、マネージャーはより大局的な視点からサプライチェーンの設計を見直す必要があります。
目指すのは、短期的なコスト削減ではなく、中長期的な供給の安定化、すなわち「サプライチェーンの強靭化」です。
- 戦略1:BCP(事業継続計画)をアップデート
あなたの会社のBCPに、「急激なコスト変動によるサプライチェーンの機能不全」というシナリオは盛り込まれているでしょうか?
多くのBCPは、「地震などの自然災害」や「サプライヤーの倒産」は想定していますが、今回の三菱商事の事例のように、「サプライヤーは存続しているが、コストが合わずに供給が事実上ストップする」というリスクは見過ごされがちです。
この新しいシナリオをBCPに追加し、具体的な対応策(代替調達先のリストアップ、緊急時の予算確保など)を今すぐ検討すべきです。 - 戦略2:サプライヤーポートフォリオを再構築する
「安いサプライヤーが良いサプライヤー」という時代は、終わりました。
これからは、評価の軸に「供給安定性」「地政学リスク」「財務健全性」といった項目を加え、総合的にサプライヤーを評価し、ポートフォリオを組み直す必要があります。
脱・コスト一辺倒評価:
各評価項目をスコア化し、サプライヤーを可視化する。
戦略的パートナーの特定:
スコアに基づき、単なる取引先ではなく「共に成長し、リスクを分担できるパートナー」を特定し、重点的にリソース(情報共有、技術支援など)を投下する。 - 戦略3:経営層へ「守りの調達」の価値を訴求する
これが最も重要かもしれません。
調達部門の貢献は、どうしても「コストを〇%削減した」という分かりやすい「攻めの調達」で評価されがちです。
しかし、これからは「守りの調達」の価値を積極的にアピールしなければなりません。
「サプライチェーンのリスクを分析し、〇〇の対策を講じた結果、将来起こり得たであろう〇〇億円の生産停止損失を未然に防ぎました」
このように、リスク回避という貢献を定量的に示すのです。
今回の洋上風力発電事業からの撤退事例は、その重要性を経営層に説明するための、またとない強力な材料になるはずです。
まとめ
今回の三菱商事の洋上風力事業からの撤退は、決して遠い世界の出来事ではありません。
この一件から私たち調達担当者が学ぶべき教訓は、極めてシンプルです。
- 予測不能なリスクは「起こるもの」と心得るべし。
グローバルな経済変動は、もはや「想定外」ではなく、戦略を組む上での「前提条件」です。 - サプライヤーを「パートナー」として遇すべし。
リスクを一方的に押し付ける関係は、必ず破綻します。共にリスクを分担し、乗り越えるパートナーシップこそが、これからの競争力の源泉となります。 - 調達は「経営マター」として捉えるべし。
サプライチェーンの強靭化は、単なるコスト削減活動にあらず。会社の存続を左右する、重要な経営課題なのです。
さあ、今すぐできることから始めましょう。
Step 1:
あなたが担当するサプライヤー上位3社について、抱えていそうなリスク(後継者問題、特定顧客への依存など)を想像して書き出してみる。
Step 2:
その3社との基本契約書を引っ張り出し、「価格スライド条項」の有無を確認する。
Step 3:
明日の朝一番、上司や同僚に「三菱商事のニュース、調達としてヤバいですよね」と、この記事をネタに10分だけ話してみる。
変化を恐れるのではなく、変化を先読みし、しなやかで強いサプライチェーンを構築すること。
それこそが、これからの調達プロフェッショナルに求められる最大の価値です。
この危機を、自社の競争力を飛躍させる好機と捉え、今日から行動を開始しませんか。
あなたの小さな一歩が、会社の未来を守る大きな力になるはずです。