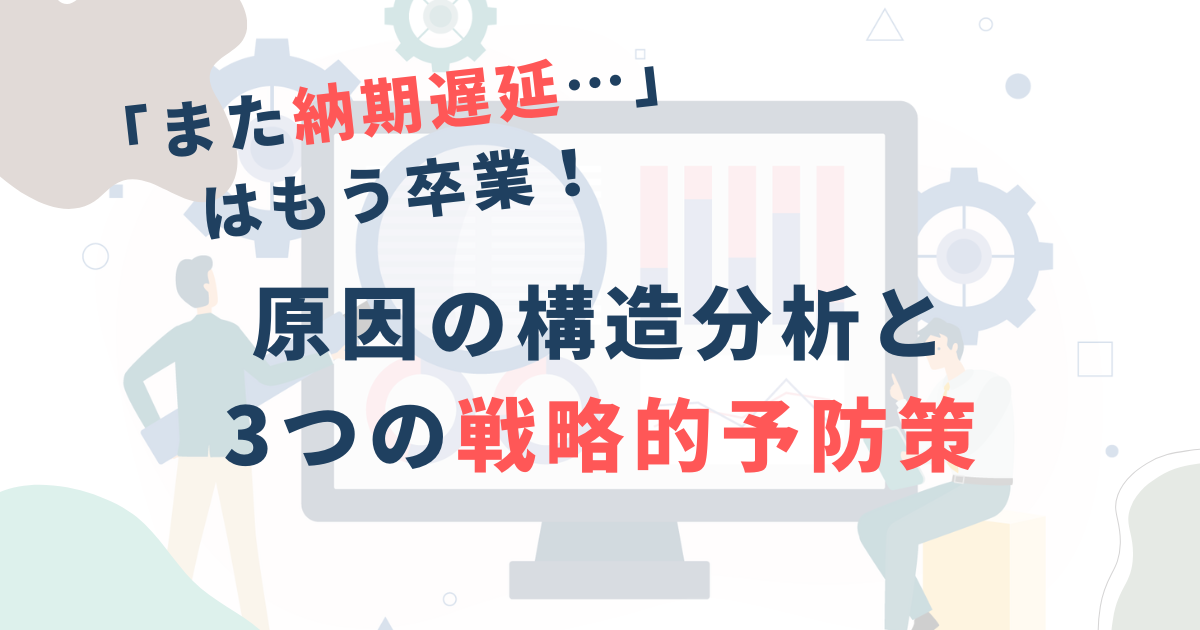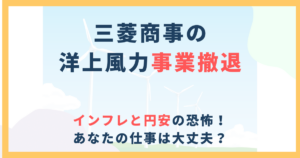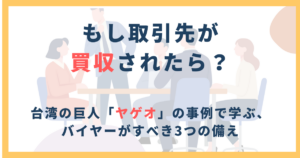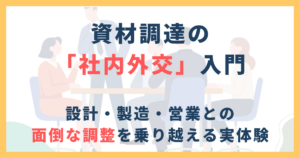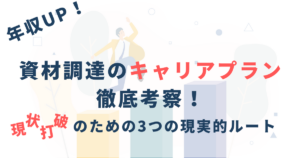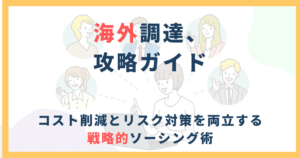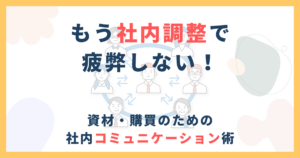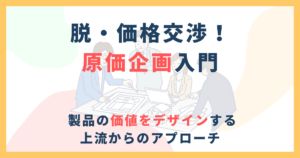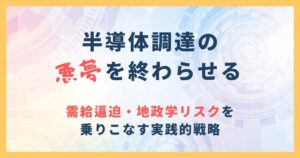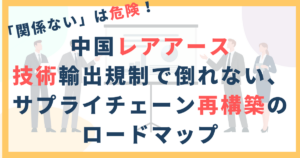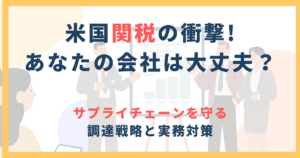またサプライヤーから納期遅延の連絡が…
本当、どうなってるんだ!
社内と社外からのプレッシャーに挟まれ、今日も調整に駆け回る。
そんなあなたの姿が、目に浮かぶようです。
何を隠そう、私自身も部品の供給がプツリと途絶え、絶望の淵に立たされた経験を何度も持つからです。
その場しのぎの対応に追われる毎日から抜け出し、問題の根本原因から対策を打ってみませんか?
この記事は、雪崩のように押し寄せるトラブルに、忙殺されているあなたのために書きました。
この記事で得られること
・納期遅延の裏に隠された「3つの構造的な問題」の理解
・明日から実践できる「3つの戦略的予防策」
・問題を未然に防ぐ「プロアクティブな調達担当者」への道筋
絶望の始まり、その納期遅延は「氷山の一角」にすぎない

「サプライヤーの工場で設備トラブルが発生しまして…」
「港が混み合っており、船の到着が遅れています」
「すみません、社内の発注ミスでして…」
これらは、納期遅延の理由としてよく耳にする言葉でしょう。
たしかに、これらは直接的な原因です。
しかし、本当にそれだけが原因でしょうか?
私の経験上、断言できます。これらはすべて、巨大な氷山の一角にすぎません。
未曾有の大災害が起きたあの時、私の会社はパニックに陥りました。
主要サプライヤー(Tier1)の工場自体は、奇跡的に被害を免れたのです。
しかし、彼らからの部品供給は完全にストップ。
理由はすぐには分かりませんでした。電話は繋がらず、メールの返信もない。
情報が錯綜し、社内からは「どうなってるんだ!」という怒号が飛び交う日々…。
数週間後、ようやく判明した事実は衝撃的でした。
問題は、そのサプライヤーに部品を供給していた三次サプライヤー(Tier3)が、完全に工場機能を停止していたことだったのです。
私たちは、自分たちのサプライチェーンの、その先の先まで全く見ていなかった。
この痛恨の経験が、私の調達という仕事に対する考え方を180度変えたのです。
目に見えるトラブルだけを追いかけても、同じ問題は形を変えて何度でも発生します。
その背後に隠れている、もっと根深い「構造的な問題」にメスを入れない限り。
思考停止の罠、あなたの会社の「3つの構造的問題」

「サプライヤーが悪い」と結論づけるのは簡単です。
ですが、その一言は、思考停止の始まりを意味します。
問題を客観的に、そして構造的に捉えるために、ここでは納期遅延の根本原因を3つのカテゴリーに分類して考えてみましょう。
① サプライヤー・マネジメントの問題
これは、サプライヤーとの「関係性の質」に起因する問題です。
- サプライヤー選定基準の曖昧さ:
とにかくコスト重視で選んでいませんか? - コミュニケーション不足:
定期的な情報交換や訪問を怠っていませんか? - 生産能力の不把握:
そのサプライヤーが本当にその量を、その品質で作りきれるのか、把握していますか? - リスク評価の欠如:
財務状況は?特定国への依存度は?
とにかくコストを下げろという製造部の号令のもと、中国の新規サプライヤーに飛びついたことがありました。
価格は既存の国内メーカーより4割も安い。まさに破格でした。
しかし、これが悪夢の始まり。
最初の納品から品質不良のオンパレード。
挙げ句の果てには、納期直前に「やっぱりその値段じゃ作れない」と開き直られる始末。
結局、国内のサプライヤーに頭を下げて特急で生産してもらい、余計なコストと時間がかかりました。
安物買いの銭失いを、身をもって体験した苦い思い出です。
② 自社内のプロセスの問題
驚くかもしれませんが、納期遅延の原因の半分は、発注者側、つまり自社内の問題であることが少なくありません。
- 部署間のサイロ化:
設計、生産管理、営業、調達がバラバラに動いていませんか?設計が直前に仕様変更し、調達が悲鳴を上げる…なんてことは日常茶飯事かもしれません。 - 需要予測の精度の低さ:
勘と経験だけに頼った需要予測は、過剰在庫か欠品、そしてサプライヤーへの無茶な要求に繋がります。 - 過度なJIT(ジャストインタイム)方式:
在庫を持たない思想は素晴らしいですが、それができるのは圧倒的な購買力とフィロソフィーを持った会社だけ。
「うちは中小企業だから、S&OP(セールス&オペレーションズ・プランニング)なんて大げさだよ」
という声が聞こえてきそうです。
ですが、そんなことはありません。大げさなシステム導入の話ではなく、営業と製造、そして調達が、週に一度30分でも顔を合わせて、販売計画と生産状況を共有する。
中小企業ほど見知った間柄。
それだけでも、サプライヤーへの無茶な発注は劇的に減るはずです。
③ 外部環境・リスク認識の問題
自分たちではコントロールできない外部要因と、それに対する感度の低さも、大きな問題です。
- 地政学的リスクや自然災害への感度の低さ
- サプライチェーン全体の可視化不足(Tier2, Tier3の未把握)
まさに、先ほどの私の失敗談がこれに当たります。
政府からもサプライチェーン強靭化の重要性が繰り返し指摘されています。
多くの日系企業が実際にサプライチェーンの見直しに着手しています。
これはもはや、一部の先進企業だけの話ではないのです。
反撃の狼煙、明日から使える「3つの戦略的予防策」

さて、問題の構造が見えてきたら、いよいよ反撃の狼煙を上げる時です!
ここからは、私が現場で実践し、効果を上げてきた3つの戦略的予防策をお伝えします。
予防策1:『守り』の強化 ― データに基づくサプライヤー管理
まず、感覚的な管理から脱却し、客観的なデータで「守り」を固めましょう。
アクション1:データによる可視化
「あのサプライヤーは、最近遅れがちだなぁ…」
ではダメです。
事実を数字で示せなければ、有効な対策は打てません。
最低でも、この指標は管理しましょう。
納期遵守率の管理
納期遵守率: 約束通りの納期に納入された件数の割合。
取得方法: 過去の納品実績データから、納期通りだった件数と総納入件数をカウント。
計算式: 納期遵守率(%) = (期間内の納期遵守件数 ÷ 期間内の総納入件数) × 100
結果: 経験上、この数字が継続的に95%を下回るサプライヤーは、何らかの構造的問題を抱えている可能性が高いです。
アクション2:定期的なサプライヤー評価
年に1〜2回、サプライヤー評価を実施しましょう。
評価項目は「QCDS」が基本ですが、現代ではこれに「R(Risk)」を加えるのがプロのやり方です。
| 評価項目 | 具体的な評価観点 |
|---|---|
| Quality (品質) | 不良率、品質改善への取り組み |
| Cost (コスト) | 価格競争力、コスト削減提案力 |
| Delivery (納期) | 納期遵守率、リードタイム |
| Service (サービス) | コミュニケーション、トラブル対応力 |
| Risk (リスク) | 財務状況、BCP策定状況、地政学リスク |
この評価結果を基にフィードバックを行うことで、サプライヤーとの健全な緊張関係と協力体制を築くことができます。
予防策2:『連携』の強化 ― 社内と社外を繋ぐプロセス最適化
次は、部署や会社の壁を越えた「連携」です。
アクション1:社内プロセスの最適化
設計段階から調達部門が関わる「フロントローディング」を推進しましょう。
「この部品は調達が難しい」「この仕様だと、あのサプライヤーしか作れない」といった情報を、設計の初期段階でインプットすることで、手戻りや無理な発注を未然に防ぎます。
アクション2:サプライヤーとの戦略的連携
サプライヤーを単なる「業者」ではなく、「パートナー」として巻き込むのです。
そのための強力な武器が 「内示・確定発注方式(フォーキャスト)」 です。
ある重要部品のサプライヤーが、いつも納期ギリギリで、品質も不安定でした。
そこで私は、6ヶ月先までの大まかな生産計画(内示情報)を共有することを提案しました。
最初は
「内示なんて当てにならない」
と渋られましたが、
「内示によって、御社も原材料の先行手配や人員計画が立てやすくなるはずです。
お互いにとってメリットがあります」
と粘り強く説得。
結果、サプライヤーは計画的に生産できるようになり、リードタイムは2週間も短縮。
品質も安定し、まさにWin-Winの関係を築くことができました。
内示によってサプライヤーは原料調達や部材の先行生産ができ、確定発注分の部材はほぼ輸送期間だけで納められるようになります。
まさに、情報を武器にした連携プレーです。
予防策3:『未来』への備え ― BCPと連動したサプライチェーン設計
最後の仕上げは、「未来」への備えです。
アクション1:リスクの特定と評価
まずは、あなたの会社にとって「これが止まったら事業が止まる」という重要部材を特定し、そのサプライチェーンのリスクを評価します。
「特定の1社に100%依存していないか?」「その工場は災害の多い地域にないか?」などをリストアップするのです。
アクション2:代替案の準備
リスクが特定できたら、供給が途絶えないように手を打ちます。
- マルチソーシング(複数社購買):
国内と海外など、複数のサプライヤーから購入する。 - 戦略的在庫:
全ての在庫を減らすのではなく、リスクの高い重要部材については、意図的に安全在庫を厚めに持つ。
こうした対策は、サプライヤーのトラブルだけでなく、「モノが届かない」リスク全般に対して有効です。
たとえば、近年深刻化している国内物流の人手不足もその一つ。
部品が製造元で準備できていても、運べなければ意味がありません。
まとめ:先手を打って能動的に行動できる調達担当者になるために

ここまで、納期遅延の根本原因とその戦略的な予防策についてお話ししてきました。
大切なのは、納期遅延を単なる「問題」として受け身で処理するのではなく、自ら仕掛けていく「管理できるリスク」へと変える意識です。
その場しのぎの火消し役から、未来のリスクを予見し、先手を打って能動的に行動できる調達担当者へ。
その変革は、今日この瞬間から始められます。
今すぐできる3つのステップ
step1:
直近1ヶ月で発生した納期遅延トップ3をリストアップし、その直接的な原因を書き出してみましょう。
step2:
その原因が、本記事で紹介した「3つの構造的問題」のどれに当てはまるか、マッピングしてみてください。
step3:
「予防策1」を参考に、主要サプライヤー1社の「納期遵守率」を、まずは手計算でもいいので算出してみませんか?
目に見える数字は、何より雄弁な説得材料になります。
この記事が、日々の奮闘に疲れたあなたの心を少しでも軽くし、明日への一歩を踏み出すための力になることを、心から願っています。
あなたのその一歩が、会社の未来を強くすることに、違いありません。