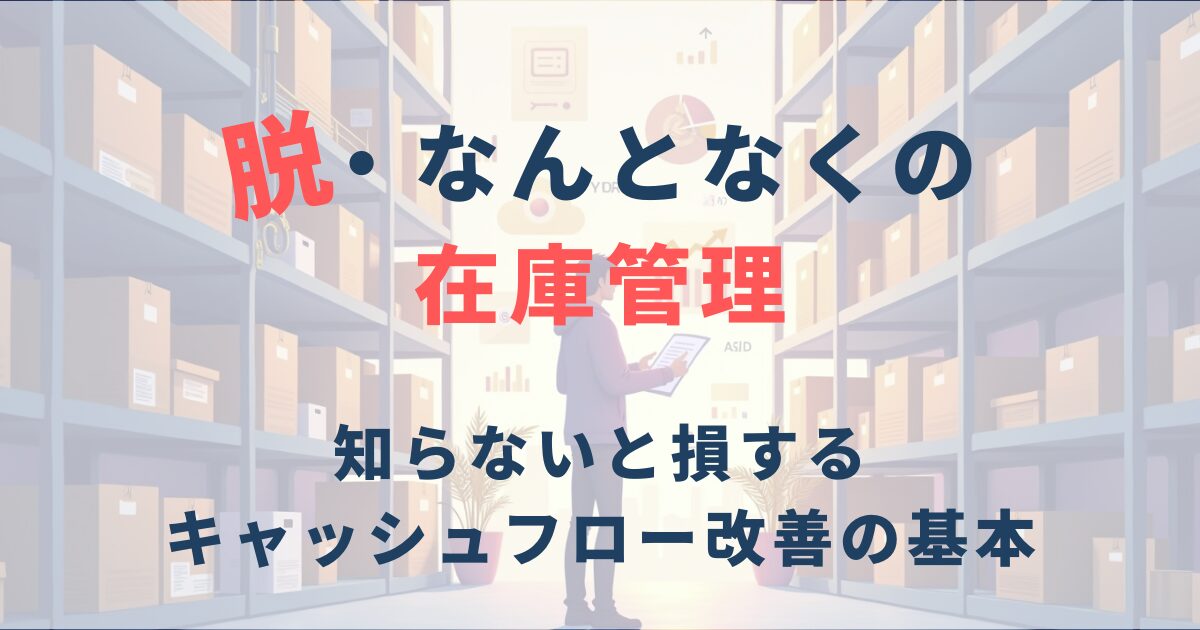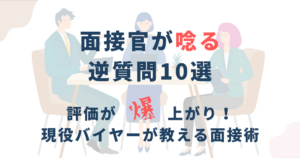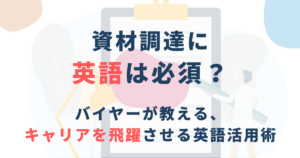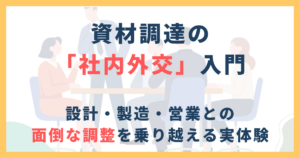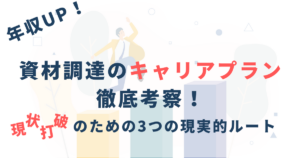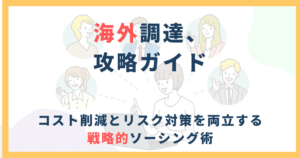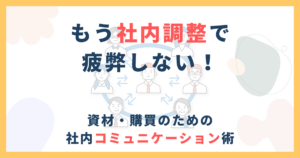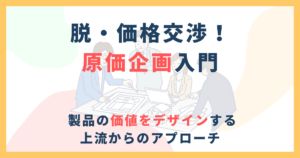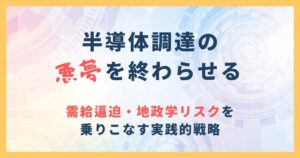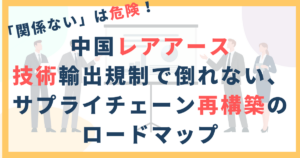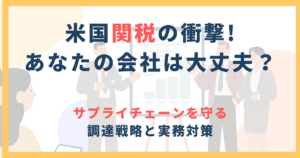「『在庫を減らせ』と上司に言われるけど、具体的にどうすれば…?」
20代の頃、資材調達の担当になって数年がたったころ、仲良くなった生産管理の三宅さんが私にそっと悩みを打ち明けました。
彼はそのプレッシャーに押しつぶされそうになっていました。
目の前には山ほどの在庫という”宝”はあるのに、肝心な”食料”(利益)がない。
そんなもどかしさと焦り。あなたも感じていませんか?
この記事で得られること
・在庫管理が「コスト削減」ではなく「利益創出」であるという、新しい視点
・感覚的な在庫管理から脱却し、数字で語れるようになる具体的な手法
・明日からすぐ実践できる、在庫最適化への最初のステップ
【結論】在庫管理は、会社の未来を救うエンジンだ

まず結論から。
在庫管理は、面倒で地味な仕事なんかじゃありません!
在庫管理は、会社の全身に血液、つまりお金の流れを生み出す「生命線」そのものです。
なぜなら、在庫管理がおろそかになり、売れる見込みのない在庫になると、会社の現金は「動かないモノ」に変わってしまうからです。
それは、会社の成長のために使えるはずだった貴重な資金が、倉庫の片隅でホコリをかぶっているのと同じ状態。正直、ゾッとしませんか?
特に、先行きが不透明なVUCAと呼ばれる現代。
内閣府 サプライチェーン強靱化の取組 でも言及されている通り、多くの企業がサプライチェーンの課題、つまり「モノの流れ」の管理にこれまで以上に注目しています。
これは、在庫管理が単なるコスト削減ではなく、企業存続をかけた経営戦略そのものになったことを意味しているのです。
衝撃の事実!在庫が、会社のキャッシュを蝕んでいる

「適正在庫」とは、欠品で生産に迷惑をかけるリスクを避けつつ、持ちすぎによるコストを最小限に抑える、在庫水準のこと。
しかし、多くの現場では、このバランスが崩れ、過剰在庫がキャッシュフローをじわじわと蝕んでいます。
在庫は資産のはずなのに、なぜコストになるの?
在庫は、会計上「棚卸資産」と呼ばれ、会社の資産の一部です。
しかし、これが売れなければ、ただの厄介者。
過剰在庫は、主に3つの形で会社の体力を奪っていきます。
| コストの種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 保管コスト | 倉庫の賃料、光熱費、管理する人の人件費など、在庫を持つだけで発生する費用。 |
| 資本コスト | 在庫を買うために使ったお金の「機会損失」。 もしそのお金が預金なら金利が、投資ならリターンが生まれたはず。 |
| 陳腐化リスク | 製品が古くなり、価値が下がってしまうリスク。 最悪の場合、廃棄費用が発生する。 |
恐怖の計算例
例えば、1億円の在庫を抱えているとしましょう。
仮に金利が1%だとしたら、何もしなくても年間100万円が「資本コスト」として消えていく計算です。
これに倉庫代や人件費が乗っかってくる。
笑えない話でしょう。
明日からできる!在庫最適化、3つの黄金ステップ

では、具体的にどうすればいいの?
難しく考える必要はありません。
まずはこの3つのステップから始めてみましょう。
【現状把握】自社の在庫レベルを正しく知る
最初にやるべきこと。
それはパソコンの画面を見ることではありません。
現場に出て、自分の目で現物を確認することです。
まずはどの部材がどれだけあるか、棚卸と現品調査による実地調査できちっと数を計測する。
これが全ての始まり。
よくある落とし穴
「データ上の在庫は100個なのに、実際に数えたら95個しかなかった…」なんてことは、日常茶飯事。
この「帳簿在庫」と「実在庫」のズレをなくさない限り、どんな高度な分析も砂上の楼閣になってしまいます。
正確な数を把握できたら、次に客観的な評価を加えます。
ここで「ABC分析」といった手法が活きてくるのです。
【適正量の算出】感覚から論理へ
現状を把握したら、次は「じゃあ、いくつ持つのが適正なの?」を決めます。
ここで勘や経験だけに頼ってはいけません。
将来の需要を予測し、「これだけは持っておかないとマズい」という最低限の在庫、つまり「安全在庫」を計算します。
うわ!難しそう…私には無理かも
大丈夫! 要は
「どれくらいの確率で欠品を防ぎたいか」と
「需要や供給のバラつき」
を考慮しているだけ。
今はExcelで簡単に計算できるよ!
Excelでの計算例
この複雑な式も、Excelを使えば計算可能です。
=NORMSINV(1-欠品許容率)*STDEV.S(使用量の標準偏差)*SQRT(発注リードタイム+発注間隔)
例えば、各要素は以下のように算出できます。
・欠品許容率:
欠品を許容できる割合(例: 100個の注文に対し90個しか供給できない場合、欠品率は10%)
・使用量の標準偏差:
使用量の実績データが入力されている範囲
・発注リードタイム:
発注してから納品されるまでの平均的な日数
・発注間隔 :
発注してから次回の発注までの日数
【維持する仕組み】発注方式の最適化
適正な量が分かっても、それを維持する仕組みがなければ意味がありません。
定期的に決まった量を発注する「定期発注方式」や、在庫が一定量を下回ったら発注する「定量発注方式」など、自社の製品特性に合ったやり方を選び、ルール化することが重要です。
孤独な管理職へ。メンバーを動かす、たった一つの視点
さて、ここからは少し視座を上げて、管理職やリーダーの方にお話ししたい。
「在庫を減らせ!」と叫ぶだけでは、現場は疲弊するだけです。
とある会社は資本効率を上げろ、と在庫削減のKPIだけを突きつけた結果、在庫の削減にばかり現場は注力しました。
過度な在庫削減は、需要の急増や予期せぬ納期遅延に対応できなくなり、欠品を頻発させました。
また、小ロット化して、生産や発注の回数を増やす必要が出てきます。
これがかえってコストを押し上げる要因となりました。
そして、イレギュラー対応の増加で業務負荷が増大し、チームはバラバラに。
そこでようやく気づいたんです。在庫は「結果」であって、「原因」ではないということに。
営業の過大な需要予測、生産計画のブレ、品質問題…。
在庫が増える原因は、調達部門の外にあることがほとんど。
だから、管理職の仕事は、他部署を巻き込み、その「原因」を一つずつ潰していくこと。
在庫という数字を通して、会社全体のオペレーションを改善する、いわば「社内コンサルタント」になるべきなのです。
時代の逆行?「あえて持つ」戦略的在庫という最終兵器
あれ?「在庫は減らすべき」じゃなかったの?
「在庫は減らすべきだ!」とここまで話してきましたが、ここで一つ、反論というか、時代の大きな変化について触れさせてください。
それは、「あえて在庫を持つ」という考え方、すなわち「戦略的在庫」の重要性です。
コロナ禍や近年の地政学リスク、貿易政策の変更で、グローバルなサプライチェーンはズタズタになりました。
これまで絶対的正義とされた「ジャストインタイム」が機能不全に陥り、「持たざるリスク」が現実のものとなったのです。
戦略的在庫とは、全ての在庫を増やすのではありません。
サプライヤーが世界に一社しかない、代替が効かない、これが無いと生産が完全に止まる…。そんな事業の生命線となる重要部品を特定し、意図的に、計画的に保有することです。
これはコストではなく、事業継続のための「保険」というべき投資でしょう。
実際に、コロナ禍で世界的な半導体不足が発生した際、この『戦略的在庫』を保有していました。
競合他社が軒並み生産停止に追い込まれる中、その会社だけは生産を継続。結果的に、市場シェアを大きく拡大することに成功しました。
これはまさに、在庫コストという『保険料』を払ったからこそ得られた、大きなリターンと言えるでしょう。
戦慄の失敗談。在庫管理3つの落とし穴

理論は分かっても、現場では思わぬ落とし穴が待っています。
ここでは、私が実際に体験したり、目の当たりにしたりした、身の毛もよだつ失敗談を3つご紹介します。
ケース1:「まとめ買いで安く」の罠
あれは、ある新製品の立ち上げ期のことでした。
販売計画はまだ不安定。しかし、営業からは「安さが武器だから、コストを下げてくれ!」と強烈なプレッシャーがかかりました。
製造部門や私はそのプレッシャーに負け、販売見込みを度外視した大量発注に踏み切ってしまったのです。
結果は、惨憺たるもの。
製品は計画通りに売れず、倉庫には長期間動かない在庫の山が…。
資材調達は、ただ安く買うだけでなく、事業計画が現実に見合っているかまで見る必要がある、と痛感した出来事でした。
ケース2:管理方法の不備による大惨事
「管理方法」がずさんだと、とんでもない悲劇が起こります。
見た目は同じ真っ白な粉の原料を、すぐ隣の棚に保管していた工場がありました。
ある日、作業者がピッキングを誤り、違う原料を使った製品が大量に生産されてしまったのです。
気づいたのは、客先での製品テストの時。客先から大クレームがあったのはいうまでもありません。
ケース3:属人化の恐怖
「あの特殊なネジの発注は、田中さんしか分からない」。
そんな属人化もまた、恐ろしいリスクです。
ベテランの田中さんが長年の経験と勘だけで発注を管理していたある部署。
彼が急に入院した途端、発注は完全にストップ。
生産ラインが止まる寸前までいきました。
個人のスキルに依存した管理体制は、あまりにも脆いのです。
まとめ:在庫管理の旅は、今日この一歩から始まる

さて、長い道のりでしたが、お疲れ様でした。
在庫管理は、一日にして成らず。
しかし、今日から始められることは、必ずあります。
まず、この3つから始めてみませんか?
・倉庫へ行き、一番場所を取っている在庫の山を、ただ5分間眺めてみる。
何か気づきがあるはずです。
・ABC分析で洗い出した「Aランク品」の担当者に「この在庫、何か困ってることない?」と聞いてみる。
・あなたの会社の「田中さん(業務を一身に背負うベテラン)」に、コーヒーでも奢って「その技、教えてくださいよ」と弟子入りしてみる。
在庫管理とは、単なる数字合わせの作業ではありません。
それは、モノの流れを通して会社の健康状態を診察し、未来をより良くするための、創造的でエキサイティングな仕事だと私は信じています。
さあ、あなたの会社のキャッシュフローを、そして未来を、その手で改善していきましょう!